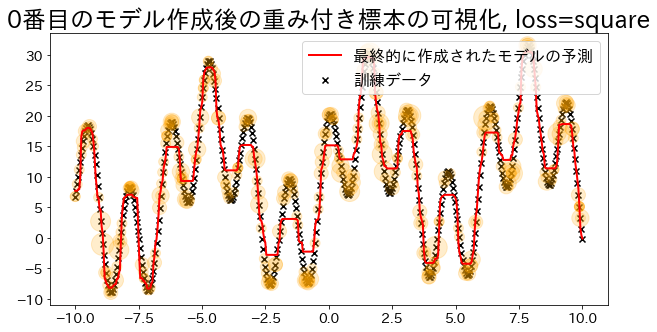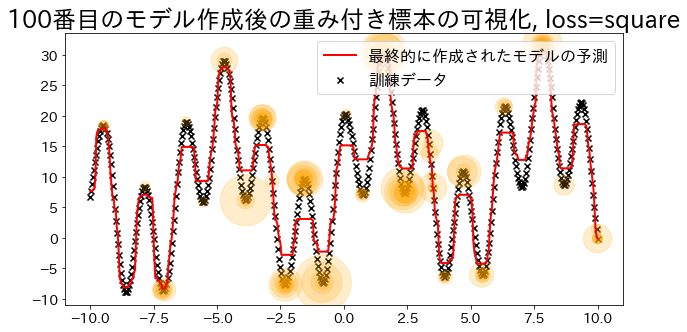2.4.4
Adaboost(回帰)
まとめ
- AdaBoost回帰(AdaBoost.R2)は予測誤差の大きいサンプルへ重みを寄せ、回帰器を段階的に改善する。
- 誤差分布に応じて重み更新が変わるため、外れ値の影響や誤差尺度の選択が性能に直結する。
n_estimatorsとlearning_rateを交差検証で調整すると、過学習を抑えつつ汎化性能を高めやすい。
直感 #
AdaBoost回帰は、誤差の大きい領域を次の弱学習器に重点学習させる仕組みです。回ごとに『苦手なサンプル』へ注意を寄せることで、単体モデルでは表現しにくい非線形な誤差構造を補正できます。
詳細な解説 #
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import japanize_matplotlib
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.ensemble import AdaBoostRegressor
# NOTE: モデルのsample_weightを確認するために作成したモデル
class DummyRegressor:
def __init__(self):
self.model = DecisionTreeRegressor(max_depth=5)
self.error_vector = None
self.X_for_plot = None
self.y_for_plot = None
def fit(self, X, y):
self.model.fit(X, y)
y_pred = self.model.predict(X)
# 重みは回帰の誤差を元に計算する
# https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/blob/main/sklearn/ensemble/_weight_boosting.py#L1130
self.error_vector = np.abs(y_pred - y)
self.X_for_plot = X.copy()
self.y_for_plot = y.copy()
return self.model
def predict(self, X, check_input=True):
return self.model.predict(X)
def get_params(self, deep=False):
return {}
def set_params(self, deep=False):
return {}
訓練データに回帰モデルを当てはめる #
# 訓練データ
X = np.linspace(-10, 10, 500)[:, np.newaxis]
y = (np.sin(X).ravel() + np.cos(4 * X).ravel()) * 10 + 10 + np.linspace(-2, 2, 500)
## 回帰モデルを作成
reg = AdaBoostRegressor(
DummyRegressor(),
n_estimators=100,
random_state=100,
loss="linear",
learning_rate=0.8,
)
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)
# 訓練データへのフィッティング具合を確認する
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.scatter(X, y, c="k", marker="x", label="訓練データ")
plt.plot(X, y_pred, c="r", label="最終的に作成されたモデルの予測", linewidth=1)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("訓練データへのフィッティング具合")
plt.legend()
plt.show()
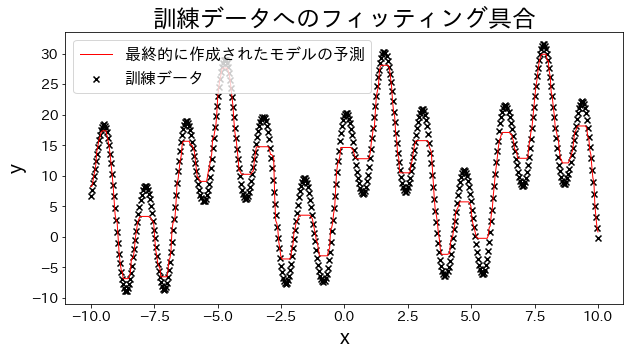
標本の重みを可視化(loss=’linear’の場合) #
Adaboostでは回帰の誤差を元い重みを決定する。’linear’ に指定した時の重みの大きさを可視化します。 重みが追加されたデータは訓練時にサンプルされる確率が高くなる様子を確認します。
loss{‘linear’, ‘square’, ‘exponential’}, default=’linear’ The loss function to use when updating the weights after each boosting iteration.
def visualize_weight(reg, X, y, y_pred):
"""標本の重みに相当する値(サンプリングされた数)をプロットするための関数
Parameters
----------
reg : sklearn.ensemble._weight_boosting
ブースティングモデル
X : numpy.ndarray
訓練データ
y : numpy.ndarray
教師データ
y_pred:
モデルの予測値
"""
assert reg.estimators_ is not None, "len(reg.estimators_) > 0"
for i, estimators_i in enumerate(reg.estimators_):
if i % 100 == 0:
# i番目のモデル作成に使用したデータに、データが何回出現するかをカウント
weight_dict = {xi: 0 for xi in X.ravel()}
for xi in estimators_i.X_for_plot.ravel():
weight_dict[xi] += 1
# 出現回数をグラフにオレンジ円でプロットする(多いほど大きい円)
weight_x_sorted = sorted(weight_dict.items(), key=lambda x: x[0])
weight_vec = np.array([s * 100 for xi, s in weight_x_sorted])
# グラフをプロット
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.title(f"{i}番目のモデル作成後の重み付き標本の可視化, loss={reg.loss}")
plt.scatter(X, y, c="k", marker="x", label="訓練データ")
plt.scatter(
estimators_i.X_for_plot,
estimators_i.y_for_plot,
marker="o",
alpha=0.2,
c="orange",
s=weight_vec,
)
plt.plot(X, y_pred, c="r", label="最終的に作成されたモデルの予測", linewidth=2)
plt.legend(loc="upper right")
plt.show()
## loss="linear"で回帰モデルを作成
reg = AdaBoostRegressor(
DummyRegressor(),
n_estimators=101,
random_state=100,
loss="linear",
learning_rate=1,
)
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)
visualize_weight(reg, X, y, y_pred)
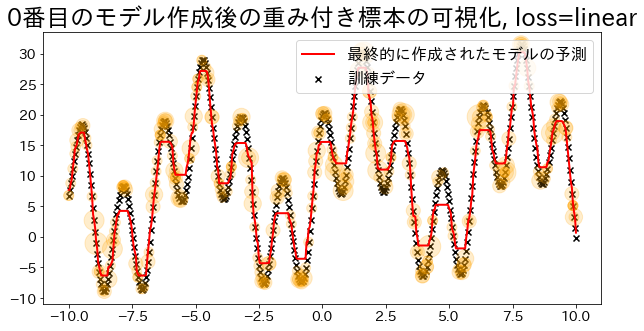
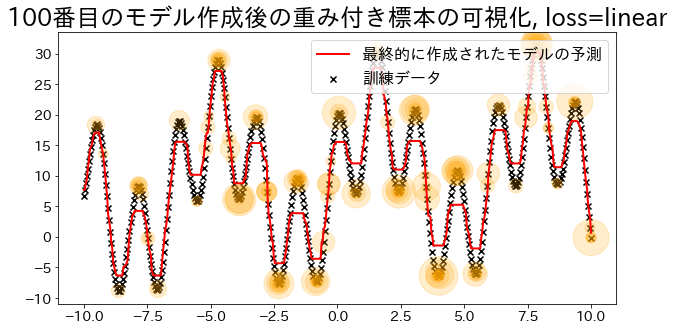
## loss="square"で回帰モデルを作成
reg = AdaBoostRegressor(
DummyRegressor(),
n_estimators=101,
random_state=100,
loss="square",
learning_rate=1,
)
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)
visualize_weight(reg, X, y, y_pred)