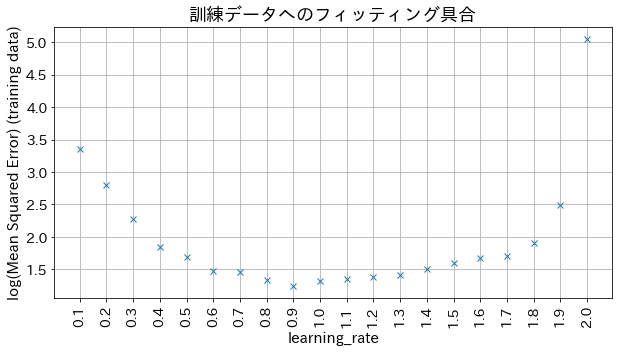2.4.5
勾配ブースティング
まとめ
- 勾配ブースティングは、現在モデルの残差(損失の負勾配)を次の弱学習器で順次学習していく加法モデルである。
learning_rateとn_estimatorsの組み合わせが、学習の進み方と過学習リスクを決める。- 損失関数の選択によって、外れ値への感度や最終予測の形が変化する。
直感 #
勾配ブースティングは、最初に粗い予測を作ってから「どこを外したか」を次の木で補正し続ける手法です。各ステップは小さな修正ですが、段階的に足し合わせることで複雑な関数形にも追従できるようになります。
詳細な解説 #
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import japanize_matplotlib
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
訓練データに回帰モデルを当てはめる #
実験用のデータを作成します、三角関数を足し合わせた波形のデータを用意します。
# 訓練データ
X = np.linspace(-10, 10, 500)[:, np.newaxis]
noise = np.random.rand(X.shape[0]) * 10
# 目的変数
y = (
(np.sin(X).ravel() + np.cos(4 * X).ravel()) * 10
+ 10
+ np.linspace(-10, 10, 500)
+ noise
)
# 回帰モデルを作成
reg = GradientBoostingRegressor(
n_estimators=50,
learning_rate=0.5,
)
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)
# 訓練データへのフィッティング具合を確認する
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.scatter(X, y, c="k", marker="x", label="訓練データ")
plt.plot(X, y_pred, c="r", label="最終的に作成されたモデルの予測", linewidth=1)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("訓練データへのフィッティング具合")
plt.legend()
plt.show()
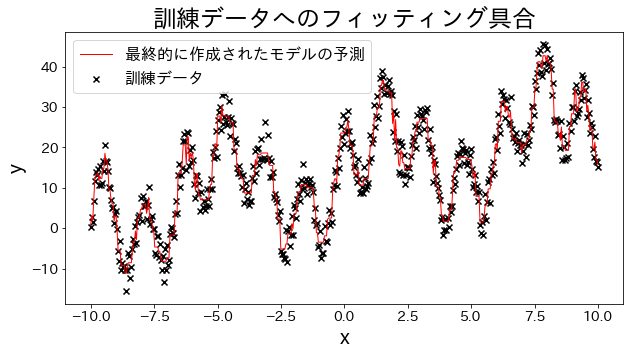
損失関数の結果への影響 #
loss を [“squared_error”, “absolute_error”, “huber”, “quantile”] と変えた場合、訓練データへのフィッティングがどのように変化するかを確認。 “absolute_error”, “huber"は二乗誤差ほど外れ値へのペナルティが大きくないので、外れ値を予測しに行かないです。
# 訓練データ
X = np.linspace(-10, 10, 500)[:, np.newaxis]
# 外れ値を用意
noise = np.random.rand(X.shape[0]) * 10
for i, ni in enumerate(noise):
if i % 80 == 0:
noise[i] = 70 + np.random.randint(-10, 10)
# 目的変数
y = (
(np.sin(X).ravel() + np.cos(4 * X).ravel()) * 10
+ 10
+ np.linspace(-10, 10, 500)
+ noise
)
for loss in ["squared_error", "absolute_error", "huber", "quantile"]:
# 回帰モデルを作成
reg = GradientBoostingRegressor(
n_estimators=50,
learning_rate=0.5,
loss=loss,
)
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)
# 訓練データへのフィッティング具合を確認する
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.scatter(X, y, c="k", marker="x", label="訓練データ")
plt.plot(X, y_pred, c="r", label="最終的に作成されたモデルの予測", linewidth=1)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title(f"訓練データへのフィッティング具合, loss={loss}", fontsize=18)
plt.legend()
plt.show()
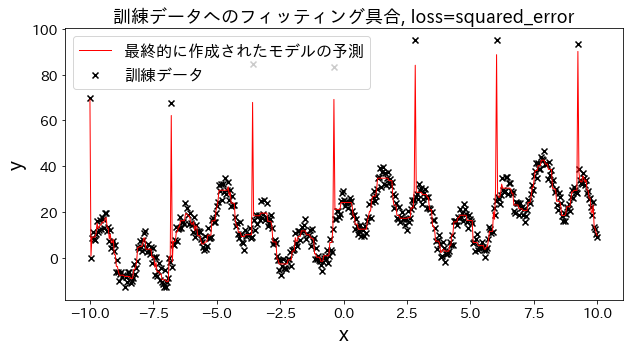
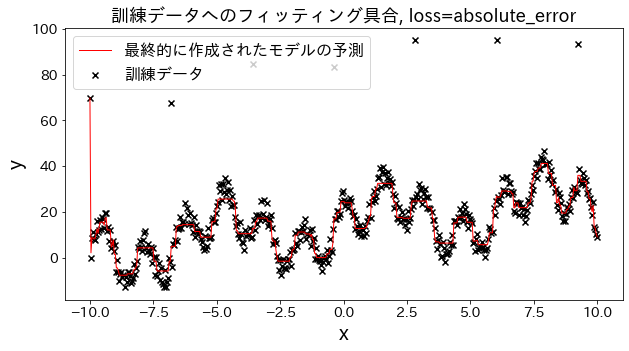
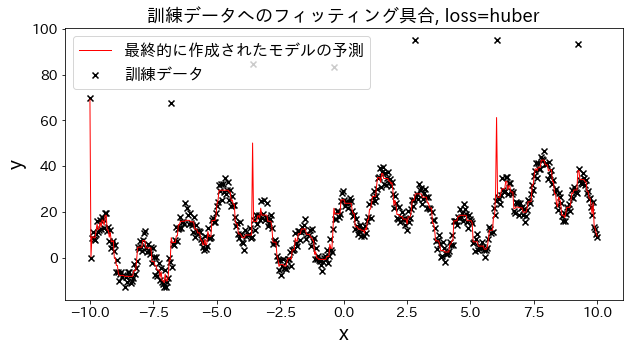
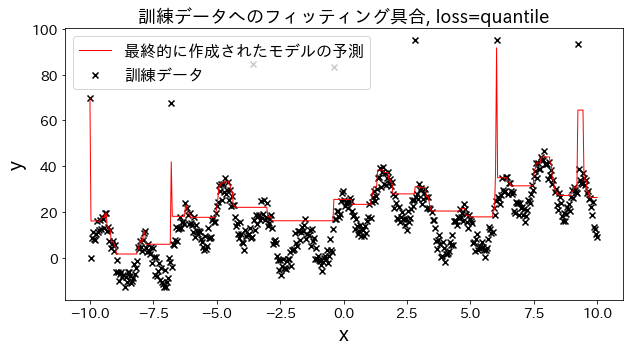
n_estimatorsの結果への影響 #
ある程度 n_estimatorsを大きくすると、改善度合いは頭打ちになる様子が確認できます。
from sklearn.metrics import mean_squared_error as MSE
# 訓練データ
X = np.linspace(-10, 10, 500)[:, np.newaxis]
noise = np.random.rand(X.shape[0]) * 10
# 目的変数
y = (
(np.sin(X).ravel() + np.cos(4 * X).ravel()) * 10
+ 10
+ np.linspace(-10, 10, 500)
+ noise
)
# n_estimatorsを変えてモデルを作成してみる
n_estimators_list = [(i + 1) * 5 for i in range(20)]
mses = []
for n_estimators in n_estimators_list:
# 回帰モデルを作成
reg = GradientBoostingRegressor(
n_estimators=n_estimators,
learning_rate=0.3,
)
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)
mses.append(MSE(y, y_pred))
# n_estimatorsを変えた時のmean_squared_errorをプロット
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(n_estimators_list, mses, "x")
plt.xlabel("n_estimators")
plt.ylabel("Mean Squared Error(training data)")
plt.title(f"訓練データへのフィッティング具合", fontsize=18)
plt.grid()
plt.show()
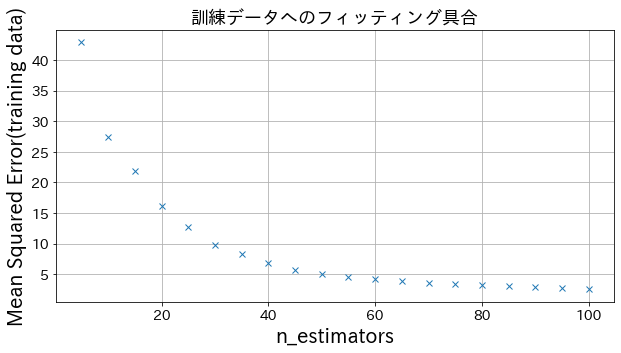
learning_rateの結果への影響 #
小さすぎると精度が良くならない、大きすぎると収束しない様子が確認できます。
# n_estimatorsを変えてモデルを作成してみる
learning_rate_list = [np.round(0.1 * (i + 1), 1) for i in range(20)]
mses = []
for learning_rate in learning_rate_list:
# 回帰モデルを作成
reg = GradientBoostingRegressor(
n_estimators=30,
learning_rate=learning_rate,
)
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)
mses.append(np.log(MSE(y, y_pred)))
# n_estimatorsを変えた時のmean_squared_errorをプロット
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt_index = [i for i in range(len(learning_rate_list))]
plt.plot(plt_index, mses, "x")
plt.xticks(plt_index, learning_rate_list, rotation=90)
plt.xlabel("learning_rate", fontsize=15)
plt.ylabel("log(Mean Squared Error) (training data)", fontsize=15)
plt.title(f"訓練データへのフィッティング具合", fontsize=18)
plt.grid()
plt.show()